やさしさ溢れるまちや場を育む信頼という土壌〜社会福祉士・コーチの実践〜

こんにちは、森山です。
このブログではWell-being(幸せ・豊かさ)を育む学びと実践をお届けしています。
- 人が自分らしく生きられる環境とは?
- やさしいまちや居場所はどのように育つのか?
- 一人ひとりが幸せに働き、暮らし、つながるとは?
そんな問いを、ソーシャルワークやコーチングの理論、そして現場での経験から紐解いています。
今回は、「優しさ溢れる街や場を育む信頼という土壌」について、一緒に見ていけたらと思います。
人は「環境」と「関係性」で育つ〜社会福祉士・コーチの実践〜

ソーシャルワーカーとして対人援助の現場で、そして地域で場づくりに関わる中で、強く感じていることがあります。
人の幸せや豊かな人生は、環境と関係性に育まれる
ということです。
- 安心できる場所がある
- 自分の声が尊重される
- 失敗しても大丈夫だと思える
- 互いを信じ合える仲間がいる
そんな土壌があると、人は自然と挑戦し、成長し、人生を自分の手で耕そうという思いが芽生え始めるように思うんです。
反対に、どんなに立派な支援計画などが作成されても対人援助職とクライエントとの間に信頼関係・協力関係の土壌が耕されていないと、変化は生まにくいように思うんです。
これは、まちづくりでも、家庭でも、職場でも同じことが言えるように思います。
問題解決だけ考えても安心感や優しさ、「幸せ」は育たない

支援の現場でも、地域の会議でも、こんな言葉がよく聴こえます。
- 「結論を出さないと」
- 「課題を整理しよう」
- 「どう合意形成するか」
もちろんこれらは、必要なプロセスです。
ですが、そこを急ぎすぎると……
- 一番大切な「思い」が置き去りになる
- 声の大きい人だけの意見が通ってしまう
- 本人の心に芽生えた違和感や当事者の声を聞くことなく進んでしまう
そして、気づけば
問題解決のために時間と労力を費やして走っているのに誰も幸せになっていない
そんな状態に陥ることもあります。
つまり、問題にフォーカスし、状況を紐解き、何をすべきかを考える議論は大事。
ただ、議論だけでは豊かさや優しさ溢れる未来は育たないのではないかと思うんです。
優しさ溢れる豊かなまちづくりは「理想とする未来」から始まる

私が大切にしている視点として
現状の問題にばかりフォーカスするのではなくて、心の底こから理想として設定する未来から考える
ということがあります。
今ある問題を前提にすると、できることは 現状維持の延長線だけになり、画期的なアイデアを実行に移したり、モチベーションの維持が難しくなります。
でも、
- どんなまちにしたい?
- どんな暮らしがしたい?
- 一人ひとりがどんな人生を送りたい?
そこを先に語り合えた時、人は「自分を信じられる未来」に向かって能動的に動き始めます。
支援も、まちづくりも、人生も、ここは同じだと思うんですね。
対話は「未来を耕す時間」→耕した後に議論をしよう

そこで問題になるのは「対話の時間」がないままに議論ばかり進めることだと私は考えています。
議論は、手段を決めるための時間。
一方で、対話は、思いを重ね、関係の土壌を耕す時間と考えるとどうでしょうか?
- なぜこの活動をするのか
- 誰の幸せにつながるのか
- どんな未来を一緒につくりたいのか
この「根っこ」が育っていないまま議論を始めると、話し合いが空回りします。
まちづくりも、人生も、土台は対話の継続と、信頼構築だと私は考えています。
信頼という見えないインフラを整え育み続けること

信頼がある場には、
- 「ここにいていい」と思える
- 自分らしさを出せる
- 頼っても、頼られてもいい
- 失敗が許容される
こんな空気が流れます。
だから、それを守り育みたいという思いが具体的なアクションとなるんですね。
このような状況が生まれると、競争よりも、協力が生まれていくんです。
反対に、
- 批判される空気
- 過度な責任追及
- 評価や序列ばかり気にする文化
そんな土壌では、挑戦は育ちません。
人の幸せも、まちの未来も、信頼の上に咲くということが、私がこの記事で伝えたかったメッセージなんです。
自分の生き方 がまちを変える〜目の前の人との対話や家族関係から〜
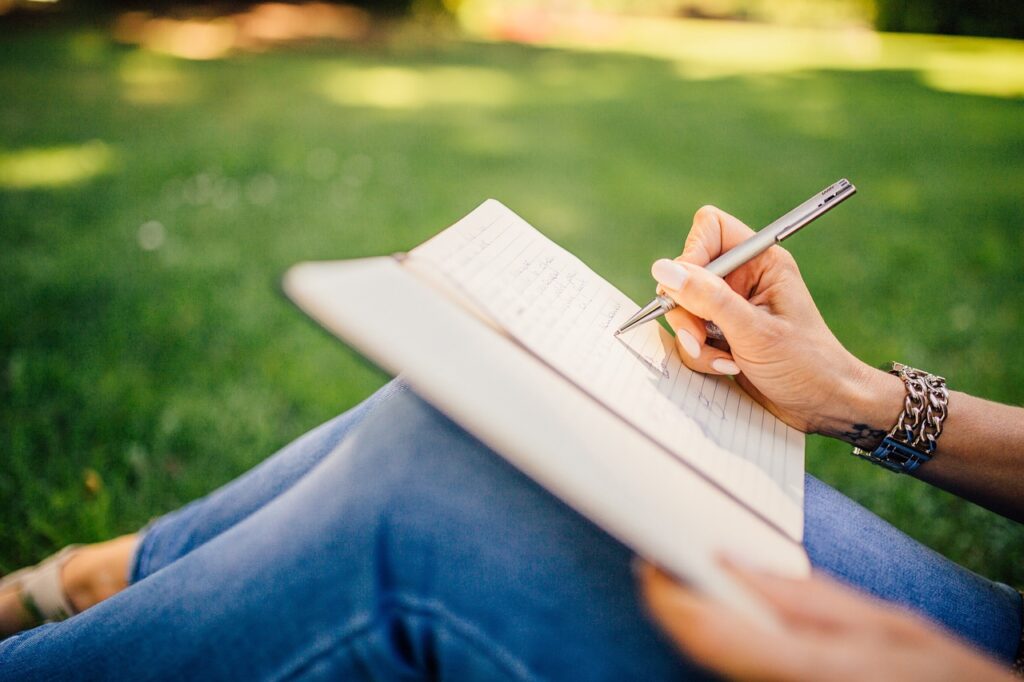
まちづくりというと、急にスケールが大きく聞こえますよね。
でも、始まりはとても小さなところから。
- 家庭での対話
- 友人との関係性
- 職場での関わり方
- 「ただ目の前の人の声を聴く」ということ
このような小さな場づくりの積み重ねが、
やがてまちの文化を育てます。
幸せな人生を生きる人が増えるほど、幸せなまちは育つ
まちは、建物や制度などでもできているのは間違いありませんが、人と人の関係性でできているということも忘れてはいけないと思うんですね。
今日からできる小さな一歩

次のミーティングや会話で、話し合いがうまくいかなかったり、協力関係ができていないと思った時…。
ぜひ「私たちはそもそも何のために話し合い、どこに向かっているのか」を考えてみるといかがでしょうか?
もしそこに何の一致点も見出せないまま具体的な議論ばかりしていると、おそらく今後優しさや豊かさが生まれることはないと思います。
だからこそ、見つめ直すべきは「一人一人の想い」であり「目指すべき方向性」だと思うんです。
ここに真摯に向き合えた時、「想い」が受け止められて「信頼」が芽生え、「協力」につながる。
すると、話し合いの場がガラッと変わります。
- 表情がやわらぐ
- 声が優しくなる
- 新しいアイデアが生まれる
このように、未来は、対話から育ちます。
これは人生にもまちづくりにも言えるのはもちろん、目の前の人との対話や家族とのコミュニケーションなどでも同じことが言えると私は考えています。
まとめ やさしさ溢れるまちや場を育む信頼という土壌

私たちこれまでまちづくりに関わってきたり、会議の場で話し合いを重ねていて思うことは、
- 施策の方向性
- 施設・設備などの在り方
- 事業の進め方
などは重要である一方で、「そもそもどこを目指し何のために話し合うの?」ということについて対話する重要視です。
行政の方や学識経験者などに混じって市民として話をするときも、「立場は違う」ということを理解し、「私はどのような役割を果たすべきか」を考え、共に未来を見据えることができれば、その話し合いは豊かなものになると思います。
組織のトップや上司がいる中で話をする時もそう。
家族の中で話をする時もそう。
みんな考えていることや思っていることは違うけど、「それぞれの立場で」「どんな未来を目指し」「自分たちに何ができるか」を共有し合えるような議論ができるといいですね!
投稿者プロフィール
最新の投稿
 価値2026年2月26日仕事とお金の悩みを解消するための煩悩を肯定術〜溢れる情報に惑わされない幸せの作り方〜
価値2026年2月26日仕事とお金の悩みを解消するための煩悩を肯定術〜溢れる情報に惑わされない幸せの作り方〜 学び2026年2月25日ソーシャルワーカー主催学びの場〜大切なものを守り育む営み〜
学び2026年2月25日ソーシャルワーカー主催学びの場〜大切なものを守り育む営み〜 起業2026年1月23日「ズボラでもひとり起業できる?」逆転の発想で貢献&収益化
起業2026年1月23日「ズボラでもひとり起業できる?」逆転の発想で貢献&収益化 起業2026年1月20日個人で稼ぐスキルとは?AI時代に自分らしく働き安定的に収益化する方法
起業2026年1月20日個人で稼ぐスキルとは?AI時代に自分らしく働き安定的に収益化する方法






